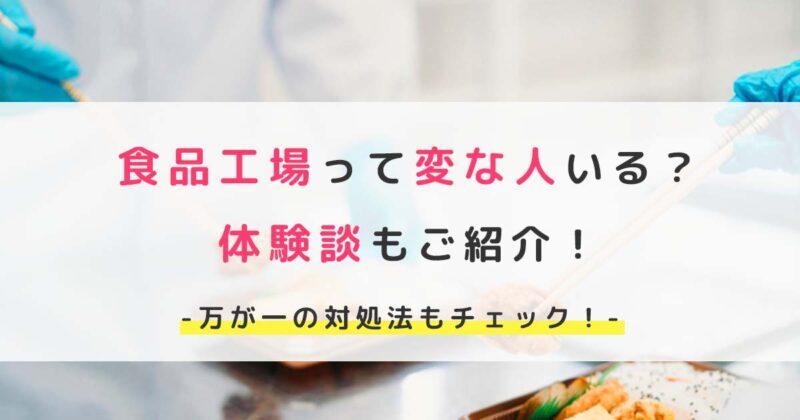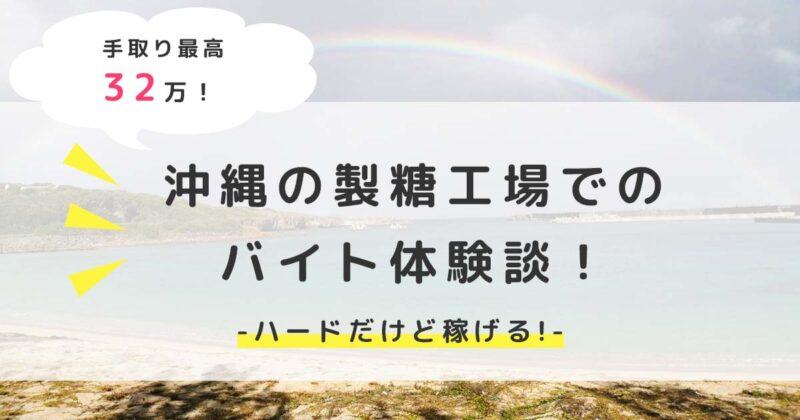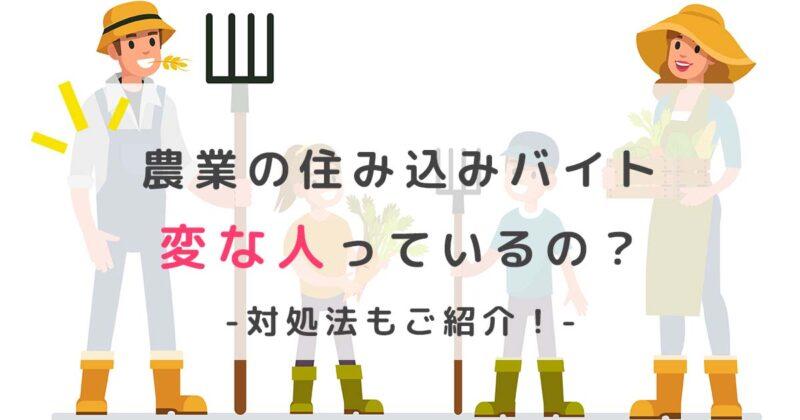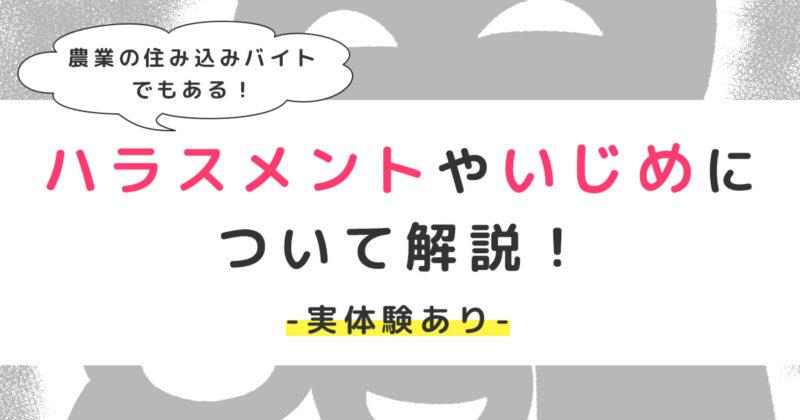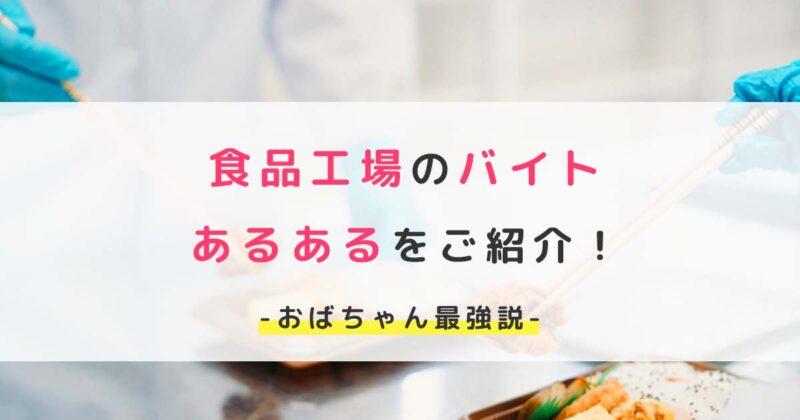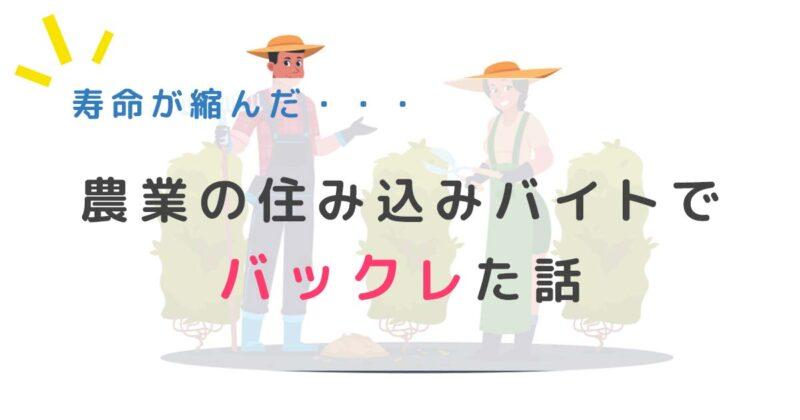こんにちは、ぴよです。
さて、工場で働いていると、しばしばこんなことを言われます。
- 工場って変な人いるの?
- 食品工場でバイトするけど、怖い人いるか心配
- 工場でクレイジーな人に絡まれたらどうしよう。
私は、製糖工場など合わせて3ヶ所の食品工場を経験してきました。
今回は、そこで実際にどんな人に会ってきたのかをご紹介していきます。
こんな方にオススメ
- これから工場でバイトをしようと考えている
- 食品工場で仕事をし始めるけど、人間関係に対する不安がある
- 食品工場で変な人に絡まれて困っている
この記事は特定の人を誹謗中傷するために書かれたものではなく、一定数このような人もいるという注意喚起という目的で書かれた記事です。
その点はご理解いただけると幸いです。
食品工場でも頭おかしい人は一定数はいる

結論から言うと、食品工場にも頭おかしい人はいます。
必ず1人はいるもんで、高確率で遭遇します。
しかも、常識の範囲を余裕で超えてきます。
おまけに社員・バイト問いません。
筆者もすでに何人か出くわし、被害に遭いました。
変な人はどこにでもいますが、割合的にやや高めのような気がします。
実際に出会った食品工場で頭おかしい人
さて、ここからは3社の食品工場で実際に出会った体験談を一部ご紹介します。
個人の特定を防ぐために、お伝えできる範囲でお話しするので、その点はご了承ください。
また、先述した通り、特定の個人を攻撃する意図で書かれた内容でもございません。
- セクハラ・パワハラ・モラハラの常習犯
- 勘違い?八つ当たりが過ぎる人
- 仕事が遅いのに仕切ってくる人
セクハラ・パワハラ・モラハラの常習犯
今まであった中で一番法律的にも倫理的にもアウトだなと思った事例です。
セクハラ・パワハラ・モラハラのトリプルパンチでやってきました。
その人がいる部署は半端なく離職率が高く、リピーターからも見限られる始末。
私は徹底無視で応戦しました。
あいさつをしないなどといった理由で、任期満了時に派遣会社の人に怒られましたが、自分の命優先です。
常識が通じない人に常識で返すのはただただ自分を消耗するだけです。
勘違い?八つ当たりが過ぎる人

とにかく感情の起伏が半端なく激しく、0か100しかありません。
100のときは、
- 間違った指示を出して、都合が悪くなると逆ギレ
- 機嫌が悪くなるとキレながら指示
- 仕事がうまくいかないと、普段話す人や当たりやすい人に怒る
...とにかく疲れます。
あまりそれが続くと、社員vsバイト論争が始まるので、これまたストレスです。
>> 詳しくは、こちらの記事もご参照ください。
これを社員がやって退けてしまうと、指示を出される側としては散々ですよね。
仕事も円滑に回らないので、いいことは一つもありません。
仕事が遅いのに仕切ってくる人
定番のやる気のある無能です。
もっと言うと、自覚症状がないやる気のある無能です。
このタイプ、中年の方に多いのですが一番厄介です。

偏見ですみません
ほぼ99%の確率で仕事を妨害してきます。
具体的には、
- 仕事をわかっていないのに、しゃしゃって指示を出し始める
- どうでもいい仕事に差し支えのないところにこだわり、それができない相手に対して怒る
- 総じて空気が読めず、本人は臨機応変に対応しているつもりが仕事を邪魔している
- 上記で仕事に支障が出ていることに気が付かない
正直これが一番害悪です。
障害物競走の途中で、いらない障害物を置いてくるような人です。
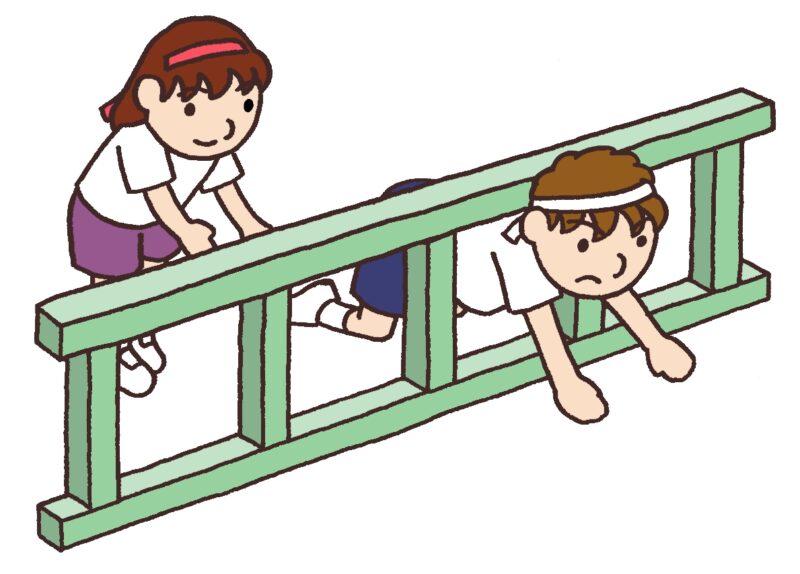

これ以上増やすな!
とにかく自分は仕事ができると思っているので、人の仕事はなぜかよくみています。
ですので、自分の仕事は遅く、まともにできないのにも関わらず、人の仕事には手を出し、口を出し、とにかくやることすべてが余計です。
食品工場にいる頭のおかしい人の対処法
さて、そんな人に頭のおかしい人に会った時の対処法をいくつかご紹介していきます。
実行する際は自己責任でお願いいたします。
- 無視する
- 正々堂々真っ向勝負
- 本当に耐えられない時は辞める
無視する
一番スマートで揉め事も起きず、平和な対処法です。
案外人って無視が一番効きます。
何かされても、言われてもひたすらシカトし続けましょう。
最初はひそひそ話していると思いますが、そのうち話しかけてこないどころか、目線を合わせるのすら避けてきます笑

意外と変なおばちゃんにやると効果的です笑
無視、すなわち相手にされないというのは誰でも傷付きます。
かわいそうな人だと思ってそっとしておきましょう笑
正々堂々真っ向勝負
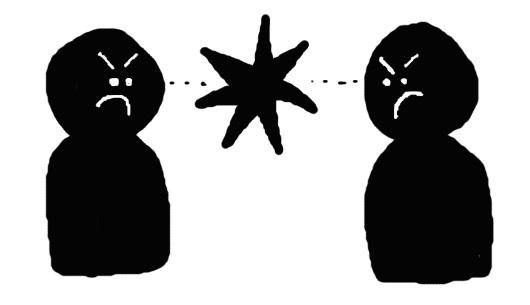
意外とこの手法も使えます。
この際、礼儀や立場、年齢の高低は一切無視しましょう。
はっきりと言いたいことをずばっと言ってスッキリさせるのも一つの手です。
その後の相手との関係に関しては自己責任にはなりますが、ダラダラ被害を被るよりはマシです。
ちなみに筆者はこの手法を使って社員に怒られましたが、逆に変な頼み事や相談事はされなくなりました。
いいように使われなくなったので、良かったといえば良かったです。

完全な円満退社はできないけどね
本当に耐えられない時は辞める
どうしても耐えられなくなった時は、逃げるが勝ちです。
限界を迎える前に逃げましょう。
ただし、バックレは非推奨です。
最終手段として使用しましょう。
食品工場にいる大半はしっかりしている人
食品工場に頭のおかしい人のいる割合が高いとは言いましたが、大半の真面目な人に比べたら大したことはありません。
私の場合、職場の人間関係に恵まれたのか、ほとんどが親切で優しい方ばかりでした。
ですので、しっかり職場の面接や見学、研修の時点でどんな雰囲気の会社なのか、よく見ることが大切です。
まとめ
食品工場では一定数ですが、頭のおかしい人はいます。
そのような人とは距離を置いて、必要最低限関わらないようにしましょう。
そして何より、一緒に働いている仲間でも、気の合う人やいい人はたくさんいます。
そのような出会いは大切にしていきましょう。